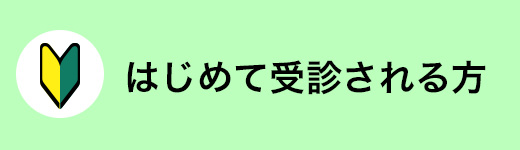副院長の生い立ち~現在に至るまでの想い

(初代院長の祖父、幸一(一番右)と5歳の私、潮田神社にて)
開業医の家に生まれた子供は継ぐように言われることも多いと聞きますが、私は父からは医師になるように言われたことは特にありませんでした。ただ祖父、父の背中を見て育ち、鶴見や川崎の地域の患者さんのために尽くす姿を見て、小学生の時点で医師、とりわけ地域に貢献できる開業医を目指すことを心に決めておりました。小学校の卒業文集(下記画像)には、「大きくなったら、大病院の部長や大学教授を目指すのではなく、地域の開業医となる」と記したのをはっきりと覚えています。
 (えらそうなことをつらつらと書いていますが・・・)
(えらそうなことをつらつらと書いていますが・・・)
小学校、中学校、高校と一貫校で学んだ私ですが、内部進学のシステムに甘んじることなく医師になるために必死で勉強を重ね、幸い医学部合格を頂くことができました。医学部では様々な科について学ぶのですが、将来地域の医師としてどの科を選択するかを考えていた時、特に興味を持ったのは糖尿病内科でした。日常の食生活がとても大事になるということ、放置していると命にかかわる合併症を引き起こすこと、発症してもしっかり管理をすれば合併症のリスクを減らせることを学び、今ではよく耳にするようになった「予防医療」(病気罹患を防ぐ、健康寿命を延ばしていくこと)に従事することをイメージしておりました。そして糖尿病内科の実習で印象的だったのが、患者さんのお話を丁寧にお聞きしているうちに患者さんの信頼を得ることができ、さらに深くお話ししているうちに治療のヒントが隠されていることが多々あったということです。「薬を使わなくても患者さんとお話しすることで治療に繋げられて、数値が良くなるなんてすごい科だ!」と感動したのを覚えています。
医学部を卒業後、2年間の初期臨床研修は糖尿病治療では全国的に有名であり、日本で初めて糖尿病の教育入院を始めたことで知られる東京都済生会中央病院で行わせて頂きました。その後糖尿病内科だけでなく地域に貢献できる総合内科医としての基礎をより強固にすべく、初期臨床研修終了後の2年間は同院で内科をより深く学ぶことと致しました。済生会中央病院で過ごした医師としての最初の4年間は、今でも「初心忘るべからず」の言葉と共に私の医師としての心の基礎に深く刻み込まれています。
その後、母校である慶應義塾大学病院の腎臓内分泌代謝内科の代謝部門(糖尿病部門)へ入局し、6年間に渡って臨床・研究の分野で研鑽を積んで参りました。大学病院で行う最新の治療をベースとした入院加療・外来加療は勿論のこと、外勤で一般企業内の医務室や健診施設の外来にも勤務し、働き盛りの方々の健康管理や健診の重要性を改めて学ぶこととなりました。糖尿病の研究においては、血糖を下げるインスリンというホルモンを分泌している膵臓の細胞について研究し、国内・海外での発表を数々行い、学を深めました。
大学出向後は、鶴見区のお隣の川崎区の基幹病院である川崎市立川崎病院の糖尿病・内分泌内科へ赴任し、糖尿病・内分泌内科及び急性期病院としての一般内科職務にもついておりました。ちょうどコロナ禍で重症患者さんが次々に入院していた時期でもあり、COVID-19自体の治療及び血糖管理と格闘していたのが思い出されます(COVID-19重症の方は糖尿病のコントロールが悪い方も多く、さらに治療でステロイドという血糖が上がる薬を使うことがあり、さらに血糖が上がってしまいます)。
そして、地域医療に本格的に従事できる自信がついたと感じ、2024年4月より当院副院長として赴任させて頂きました。糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症を始めとする生活習慣病は勿論のこと、一般内科や甲状腺疾患(甲状腺機能低下症(橋本病)、甲状腺機能亢進症(バセドウ病))もしっかりと拝診させて頂いております。当院に長く通院されている患者さんからは「先生のことは小さい頃から見たことあるわ」や「おじいちゃんの代からずっと家族みんなお世話になっているので宜しくね」などのお言葉をかけて頂き、少々恥ずかしくもありますが大変元気づけられ、嬉しく思っております。
生活習慣病は特に慢性疾患であり、長くお付き合いしていく病気でもありますので、ある意味患者さんの人生に関わり続ける側面があると考えております。『病を診ずして人を診る』という言葉があるように、病気ばかりを追うのではなく患者さん一人ひとりの背景をよく考え、お気持ちやご意見をじっくりとお聞きしながら、地域の皆様の人生に寄り添っていけるような『生涯のかかりつけ医』を目指して日々鍛錬・精進し、粉骨砕身頑張って参ります。